学生から静かな叫び<2>「学生支援の実態」
安心できる居場所づくりを
「相談した意味、あるのかな」―。昨秋、本学の学生支援室へ相談した4年生のAさんはこう話す。ゼミや卒論で耐えきれない辛い経験をして、逃げるように支援室に駆け込んだ。しかし、相談員から返ってきた言葉は「ゼミならきっと単位はもらえるから、もっと頑張ってみて」―。すっかり話をすり替えられてしまった。
Aさんは以前にもゼミの担当教員から精神的に追い込まれ教務課の職員に相談した。その時は「(当該教員に)こちらから注意してもいいけど、あなたの立場が無くなるかも」と言われてしまい、引き下がらざるを得なかった。
そして前述の学生支援室での話だ。あの時は相談員に「単位の問題ではないんです」と切り返す気力も失せていた。「どこに行ってもだめ。どうして良いか分からず悲しかった」と、当時の苦しい胸の内を吐露する。
本学には全16学部と通信教育部に、学生生活全般の相談を受け付ける「学生支援室」が設置されている。だが、その認知度は44%(本紙調査)と低く、Aさんのように「相談に行って損をした」というミスマッチも起こりがちだ。それはなぜか―。
東京・市ケ谷の日大会館に拠点を置く「学生支援センター」に取材すると、学生支援室の実態が見えてきた。学生支援室には相談内容に応じて学部内の所管部署と連携し学生の相談内容に対処する「コーディネーター」がいる。だが経済、国際関係、三軒茶屋キャンパス(危機管理・スポーツ科学部)の4学部以外には、福祉専門職(社会福祉士・精神保健福祉士)の資格を有する専門コーディネーターがいない。そのため学生課の職員や事務の派遣職員らがコーディネーターを兼任しているのが実情だ。
兼任職員の多くは「日本大学インテーカー」という学内資格を持つ。年2回、学生相談に関する実習形式の研修を修了すれば付与される学生支援の資格だが「年々学生の悩みは多様化、深刻化してきており、専門人材の配置は必須」と本部学生支援センターの主任カウンセラー・沖田肇さんは訴える。本部の学生生活委員会において「各学部に専門コーディネーターの配置を」と要望しているが聞き入れてもらえないという。
現場への理解形成を
専門人材の配置が実現しない理由を、本部学生課で学生支援に関わる内田修さんに聞くと「専門コーディネーターの必要性について各学部の理解が進んでいないことが要因」と話す。
コーディネーターは学生のニーズを聞き取り、その内容をカウンセラーに話をつなぐか、教務課に取り次ぐかなど問題解決に向け各部署に引き継ぐ役割がある。現状では兼任職員の所属部署のみで対応を終わらせ根本的な解決が図れなかったり、派遣職員のため相談内容の継続が難しかったりするなど、問題が多い。まずは相談者に対する専門的なフォロー体制をしっかり整えるべきだ。
学生ファーストなら・・・
学生の悩みが複雑化しているからこそ、何度も相談機会を設けるなど「安心できる居場所づくり」が求められる。学生のニーズよりコストや効率性を重視しては「学生支援」の役割を果たせない。
冒頭のAさんは、今もゼミに顔を出すことが不安だという。勇気を出して相談に行っても返って悩みが深まってしまった、Aさんのようなケースはあってはならないことだ。本学は新体制で「学生ファースト」を打ち出している。それならば、本当に困っている学生にこそ手を差し伸べるべきだ。悩んでいる学生に寄り添い、丁寧に相談者の話を聞く。そんな親身な支援体制を根付かせることが大切だ。
日大新聞社からのお知らせ
タグから検索
- 卓球
- 理工
- 競泳
- 特集・企画
- イベント
- 空手
- 柔道
- 文理学部
- スポーツ科学部
- 脚本家
- キックボクシング
- トランポリン
- インタビュー
- バレーボール
- 相撲
- 薬学部
- 日芸
- 就活
- 連携プロジェクト
- ピックアップ
- レスリング
- 女子相撲
- 馬術
- ミス日本
- 自主創造
- NHK杯全国高校放送コンテスト
- オンデマンド配信
- ハンドボール
- 通信教育部
- ラグビー
- 野球
- 卒業式
- Nコン
- 国際関係学部
- 陸上
- シンポジウム
- チアリーディング
- 危機管理学部
- 医工連携
- 芸術学部
- 駅伝
- 特別研究
- 弓道
- AI
- 学長
- レストラン
- 自転車
- 日大改革
- 重量挙げ
- ボート
- 理事
- よりみち
- ゴルフ
- 学部祭
- アメフット
- 体操
- 志願者数
- 準硬式野球
- 射撃
- FD
- スケート
- 水泳
- 学部長
- 生産工学部
- 国体
- 自主創造プロジェクト
- 歯学部
- 夏の甲子園
- 特許
- 法学部
- 芸術
- 工学部
- 松戸歯学部
- 高校総体
- 卒業生
- 学生社会
- 総合
- バスケットボール
- 女子サッカー
- 理工学部
- 入学式
- ロボコン
- 付属校
- 男子サッカー
- 商学部
- ローイング
- 国家試験
- テニス
- 生物資源科学部
- バドミントン
- 経済学部
- ヨット
- スカッシュ
- ボクシング
- 医学部
- フェンシング
- スキー
- サーフィン
- 端艇



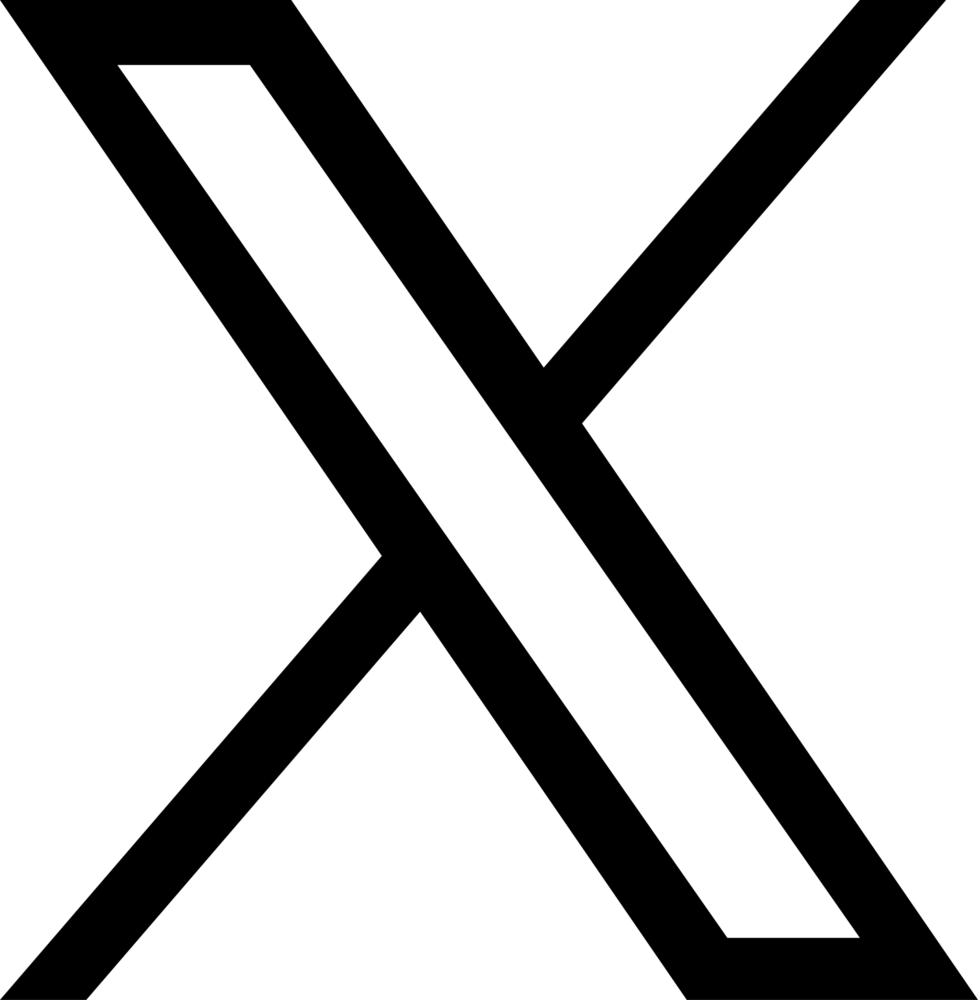





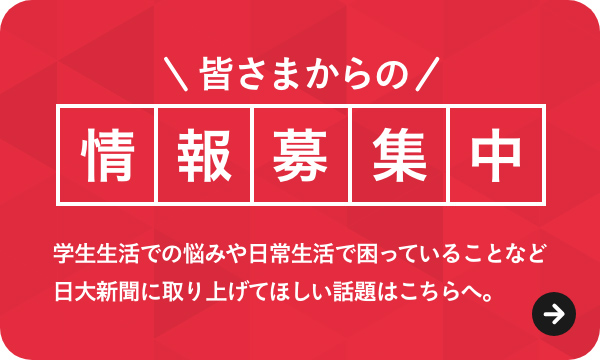


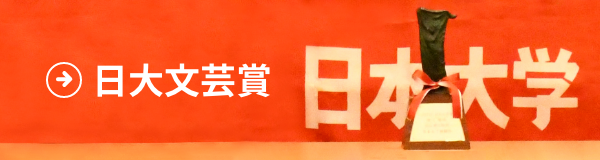

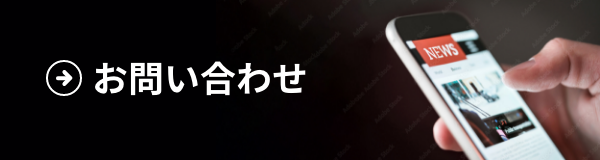

ご意見・ご感想はこちらから