日大新聞で振り返る100年<第1部 本学と日本の歩み> <5>「日大紛争」
「日大新聞」再起へ
戦後復興や新制大学への移行の混乱が落ち着き、本学は新たなる目標として規模拡大や教学内容の充実を掲げた。本紙1963(昭和38)年1月15日付の新年号(第662号)の年頭所感でも、古田重二良会頭は「世界的総合大学の基礎を築きあげ、その実現を計らなければならない」と語っている。本学は中期計画を策定、目標達成に向けて走り出した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「団塊世代」の入学期を迎え、規模拡大が一段と続いた本学。教室に収まりきらないほどに学生数が増加する一方、休講が多いこともあって学生の学修環境は悪化。大学への不満はマグマのように膨れ上がっていった。
そんな中、68(同43)年4月15日に大事件が発覚する。各紙報道機関が本学の「20億円使途不明金」の記事を報じたのだ。以前から大学のマスプロ化や学費値上げへの不満、集会や出版物の許可制への反発などから学生運動は頻発していたが、この事件報道を受けて、同年5月27日には経済学部前で学生が最大約3千人集まるほど大規模なデモが発生した(同年5月30日付号外)。学生の怒りはついに頂点に達したのだ。その後も本学内のいたるところでバリケードが築かれ、デモや集会も激しくなっていった。
この異常事態を沈静化するため、同年9月30日に両国日大講堂で大衆団交が開かれる。学生が要求した、自治活動の制限撤廃やヤミ給与の解明などに関して大学側が受け入れ、大衆団交で確約。さらに12月6日に寄附行為の改正案が発表され、本学は改革への一歩を踏み出したかのようにみえた。しかし、本紙は同月15日付(第753号)の論説で疑問を呈する。会頭制度を廃止し、会長・理事長・総長の三本柱の運営体制に改正した寄附行為は、現状と大きな違いはないとの論を展開した。
69年(同44)に入ると学生運動は沈静化に向かったが、本紙は「大学当局の一方的な休刊決定など諸々の事情により新聞の発行を継続していくことが不可能である」と判断し、70(同45)年2月15日付で「廃刊号」を発行。歴史に幕を閉じかけた。
ところが、本紙はわずか3カ月後に復刊する。約50年の歴史を持つ日大新聞の灯を「学生記者自らが消してはならない」と山口裕久さん(73歳、72年法卒)らが主力となり再出発を果たしたのだ。しかし、そこには当然新たな苦難が待っていた。
苦難の道のり
取材に行くと、一部の学生からは「大学の犬」「御用新聞だ」と激しく非難され、大学の職員からは闘争を起こした学生側だと白い目で見られる日々。顔見知りの学生にすら「なにをしているんだ!」とカメラからフィルムを抜かれることもあったと山口さんは振り返る。思うように取材や新聞発行のできない日々は、半年以上にも及んだ。
学生からも大学からも認められない現実。「これでは大学が再生したとしてもうまくいかない」と悟った山口さんらは、まずは大学の新しい動きを報道する、意地でも新聞発行を毎月続けるとの一心で臨んだ。その努力が報われ「廃刊号」前に取り消されていた第三種郵便物の認可が71(同46)年1月26日付で再び下りた。
山口さんらは「大学とともに歩む」という姿勢から、過去の出来事に執着することは適切ではないと考えていた。ただ、同時に本紙は大学をいい方向に変えるための見張り役にならなければいけない―。
創刊50年を目前に一度は廃刊へと傾きかけたが、山口さんらのねばり強い姿勢が復刊への道を開いた。「学生による学生のための新聞」。創刊当初からの使命の下〝新生〟日大新聞は歩み始めたのだった。
日大新聞社からのお知らせ
タグから検索
- 卓球
- 理工
- 競泳
- 特集・企画
- イベント
- 空手
- 柔道
- 文理学部
- スポーツ科学部
- 脚本家
- キックボクシング
- トランポリン
- インタビュー
- バレーボール
- 相撲
- 薬学部
- 日芸
- 就活
- 連携プロジェクト
- ピックアップ
- レスリング
- 女子相撲
- 馬術
- ミス日本
- 自主創造
- NHK杯全国高校放送コンテスト
- オンデマンド配信
- ハンドボール
- 通信教育部
- ラグビー
- 野球
- 卒業式
- Nコン
- 国際関係学部
- 陸上
- シンポジウム
- チアリーディング
- 危機管理学部
- 医工連携
- 芸術学部
- 駅伝
- 特別研究
- 弓道
- AI
- 学長
- レストラン
- 自転車
- 日大改革
- 重量挙げ
- ボート
- 理事
- よりみち
- ゴルフ
- 学部祭
- アメフット
- 体操
- 志願者数
- 準硬式野球
- 射撃
- FD
- スケート
- 水泳
- 学部長
- 生産工学部
- 国体
- 自主創造プロジェクト
- 歯学部
- 夏の甲子園
- 特許
- 法学部
- 芸術
- 工学部
- 松戸歯学部
- 高校総体
- 卒業生
- 学生社会
- 総合
- バスケットボール
- 女子サッカー
- 理工学部
- 入学式
- ロボコン
- 付属校
- 男子サッカー
- 商学部
- ローイング
- 国家試験
- テニス
- 生物資源科学部
- バドミントン
- 経済学部
- ヨット
- スカッシュ
- ボクシング
- 医学部
- フェンシング
- スキー
- サーフィン
- 端艇



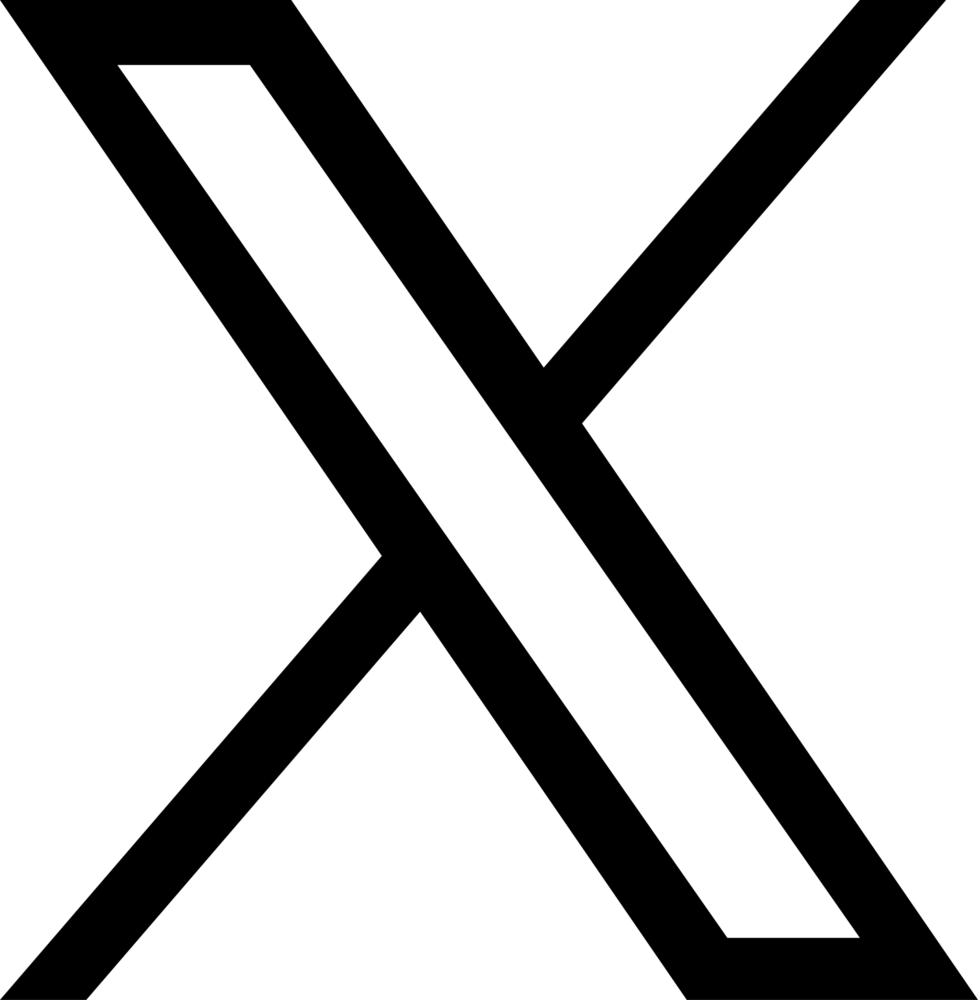





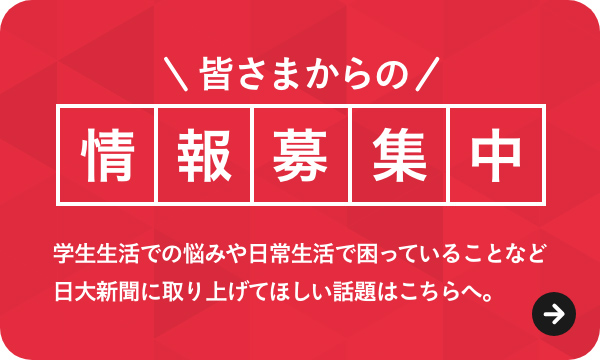




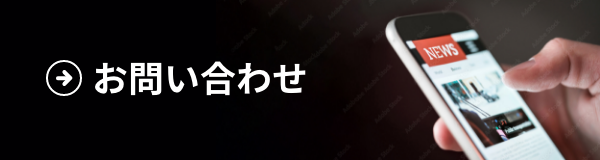

ご意見・ご感想はこちらから